セルフブランディングのための自費出版
出版科学研究所の発表によると、2018年の紙の出版販売額は約1兆2,800億円台になると見込まれているそうだ。前年度に比べて6.4%の落ち込み。この内訳は、書籍が約6,900億円、雑誌が約5,800億円を占めている。いずれも前年からはマイナスとなり、書籍は12年連続、雑誌は21年連続で前年割れになる。雑誌はオワコンとも言われるようになった。まさに出版不況真っ只中な状況だ。
しかしながら、確かに出版販売額は減少しているかもしれないが、本を出版しているというステータスはあまり変わっていないような気がする。皆さんの周りで本を出版している人はいるだろうか?もしいるならば、その人はそのジャンルで一目置かれる人になっていないだろうか?ベストセラーとしてメディアで取り上げられるようなことがなくても、名刺交換の際に本を出していると聞くと、少しその人への見方が変わらないだろうか?
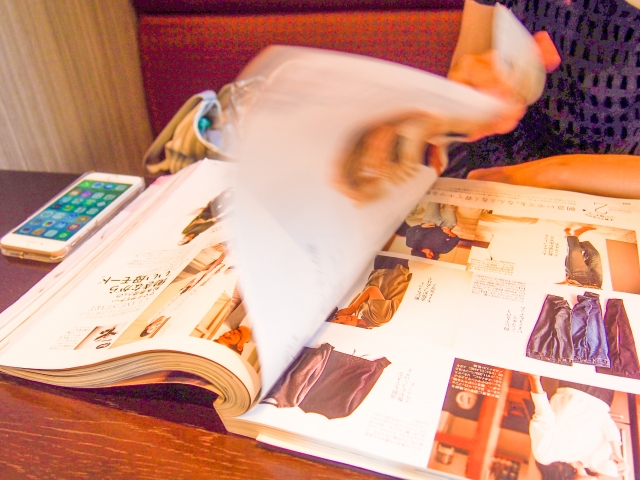
本を出版している=自己ブランディングにつながる
タレントや芸能人が本を出版し、優雅な印税生活などと揶揄されている場面を見たことがある方も多いだろう。しかしながら実際はどうだろうか?よく言われる「商業出版」。これは総じて、出版に際して著者が印税をもらえる出版形態のことを言う。出版社から本を上梓する場合、基本的には印税が支払われる。出版社の規模などによるが、著者が受け取る印税はおおよそ本の定価の8%から10%が多い。業界的には10%が上限で、それは大手出版社の場合がほとんどだ。中小規模の出版社だと数パーセントが関の山だ。また、印税が支払われるのは、まず初版の印刷部数に対してであり、定価1,000円の本を5,000部出すと、初版印税が50万円となる。この金額を見ても、「優雅な印税生活」というのは考えにくい。そんな生活は、一部の著名な商業作家くらいのものだろう。出版社によっては、初版発行後6カ月後の支払いだったり、初版発行時と数カ月後に半金ずつといった取り決めのところもある。初版が5%で二刷から10%になるといった設定もある。近年の刷り数は減少しており、初版1万部といったことはほとんどないといっていい。一般的には初版1,000部くらいからだろう。
前述したように、本を出しているというのは相手にインパクト与えることができる。故に著書を出版するのは、ビジネス的に大きな影響があるのだ。自社の商品やサービス、ビジネス、自分自身のことや会社の理念などを知ってもらうことで、親身な感覚が読者に生まれる。一般読者だけでなく、自社の社員や家族にも好影響を与えるだろう。その意味で、起業家やコンサルタント、士業(税理士、会計士、弁理士など)の専門家にとっては、著書があるのとないのとでは、その権威付けに大きな違いが出ると言える。。あの松下幸之助氏や著名なコンサルタント船井幸雄氏も著書をたくさん出版することで、自社と自己のブランディングを行なっていた。

著書を出すのは印税生活を狙うためだけではない
1日平均200冊の新刊が出版されていると言われる昨今だが、出版社としては部数が読めない、知名度の低い会社や経営者の本をすぐに刊行してくれるわけではない。当然売上が見込めて、重版になるかどうかを判断基準にする。そこで商業出版に乗らない著者にとっての次の策が「自費出版」である。書籍をつくり印刷してもらい、印刷分を著者自身がが引き取り、知人や友人などの献本して読んでもらう。自費出版は、当然印税の支払いはない。国際標準図書番号のISBNコードも付かない。商業出版は出版社側が編集、出版費用を持つのが基本だが、自費出版の場合その費用200~300万円を出版社に支払うことになる(約200ページの本を出版する場合の費用感。出版社により費用の増減あり)。執筆を生業としているならば、できるだけ商業出版を狙い売れっ子になりたいというのが本音だろう。しかし、経営者やコンサルタント、士業の皆さんで言えば、売れっ子になるよりも自社のブランディングをする方が実利に繋がるはずだ。であれば、自費出版の費用を広告費と考え、自社や自身のブランディングに活用することを考えることをお勧めしたい。
昨今では、amazon社が展開する電子書籍のサービスで、誰でも本を作り世界へと配信することができる。自費出版であっても世界市場を狙うことができるのだ。編集や校正、執筆だって外部に依頼することもできる。この潮流に乗り、経営者、起業家、コンサルタント、士業といったみなさんには、是非とも本を作って自己ブランディングを確立して頂きたい。
企業出版でセルフブランディング
http://www.g-rexjapan.co.jp/corporate_publishing201808.pdf
関連記事
-

-
出版社の本の電子化を考える
2017/10/01 |
このところ、出版社をまわって様々な話を聞かせてもらっています。 その中で本の電子化ついても意見を伺...
-

-
飲み会もオンラインでやる時代がきた
2019/10/01 |
今日はこのこと↓について、30人ほどの方と話をしました。 建築現場をアートで彩る「まちかど障が...
-

-
教科書・教材のデジタル化に思うこと
2015/09/28 |
北欧諸国などで採用されている「Bring Your Own Device(BYOD)」 ご存知です...
-

-
世界最大のプラットフォームで自己ブランディング
2018/09/30 |
本は自分で簡単に出せる時代 自分が執筆した作品を、amazonが提供している電子書籍「kindle...
- PREV
- 序破急を使って構成、章立てを考える
- NEXT
- ブルガリアと日本の架け橋eブック






































