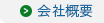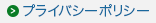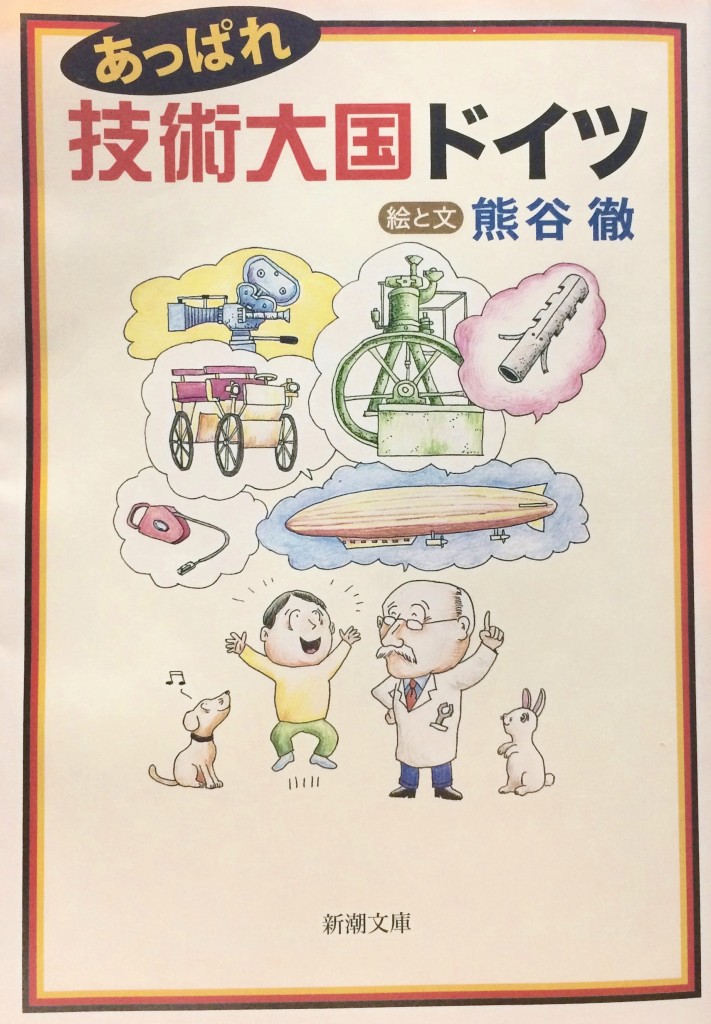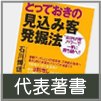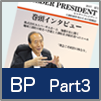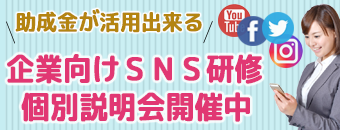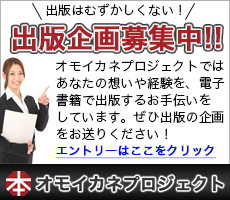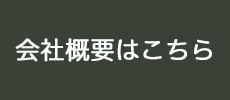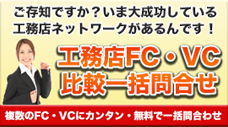テュフトラーになろう
1990年からフリージャーナリストとしてドイツに在住している、熊谷徹氏の著書「あっぱれ技術大国ドイツ」を読みました。
僕はドイツ製品が大好きです。
車からカメラ、刃物、 ステーショナリー、腕時計、髭剃り、歯ブラシ、懐中電灯、そしてケルヒャーなどなど、様々なドイツ製品にお世話になっています。あ、食べ物とビールでもお世話になっていますね(笑)
ドイツの製品に共通している「堅牢さ」と「優美さ」と「安定感」、そこに魅力を感じます。派手さや華美な装飾は無いけれど、ドイツの製品には日本製品にも見られる細部へのこだわりと、高い技術力を見ることができます。この本には、そのドイツの技術革新と隠れた底力が書かれています。
ドイツの経済を語る上で重要な存在となるのが、「Mittelstand (ミッテルシュタント)」
具体的には従業員数が500人未満、毎年の売上高が5,000万ユーロ(約60億円)未満の「中規模企業」のことを指すそうです。
2007年の勤労者2,960万人うち、2,090万人がこのMittelstandに雇用されていたそうで、まさにドイツ経済の屋台骨となっているのがMittelstandなんですね。
Mittelstandの成功例として、第1章でベーヴェ・システック社という会社が紹介されています。
ベーヴェ・システック社は、文書の自動封入の機械では世界のトップメーカーであり、いわゆるB2B(Business to Business)企業。一般消費者の知らない法人分野で、極めて大きな存在感を発揮しています。世界シェアを占める無名のMittelstandがニッチ市場に特化して、数多く活躍しているのがドイツなんですね。
そしてMittelstandが成功するキーワードが「Tüftler (テュフトラー)」
TüftlerはTüfteln(テュフテルン)とう動詞から来ている言葉で、この動詞のニュアンスを一言で的確に表現する言葉は日本語には無いそうです。デンマークのhygge(ヒュッゲ)みたいですね。
熊谷氏曰く「細かい手作業や試行錯誤、実験、色々と考えることによって、何か新しいモノを生み出したり、難しい課題についての解決方法を見つけようとしたりすること」
これこそがドイツ人のものづくり精神の根幹であり、その精神が堅牢さと優美さと安定感のある製品を生み出すんですね。
その点でいくと日本人にも同様の精神が息づいていると思います。
日本にも中小規模の会社が多数存在し、その会社でなければ作れないものニッチなモノを生み出しています。
そこには匠の技を持った日本版のTüftlerたちが存在しています。
これからは、ライバル会社の方を向いて日夜競争に明け暮れる仕事はしたくないなぁと思うのです。
ニッチなモノやコトに特化し尖鋭的で独創的な仕事を続けることで、大手企業との競争を避けることができると思います。そしてその仕事がただ自社の売上や規模を大きくするだけでなく、遠いどこかの人たちにハッピーを届けることが出来たら、働く自分たちも幸せですよね。
これから僕たちも「Japan Tüftler」となって、世界にハッピーを届ける仕事がしたいと思います。
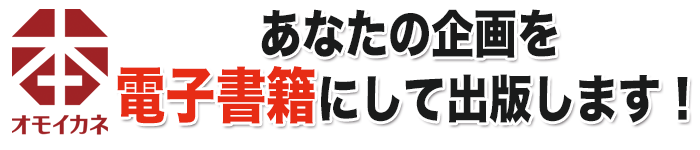
Twitterもチェック