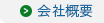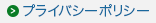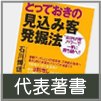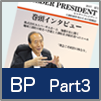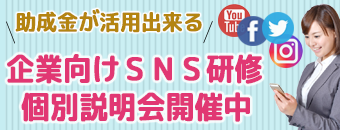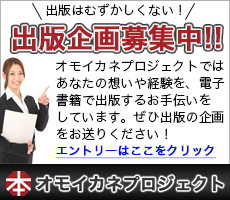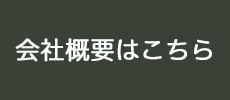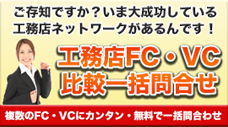ICTと経験をスマートに融合させる農業を
明けましておめでとうございます。
今日から仕事始めの方も多かったのでしょうね。
僕は明日から本格始動なので、今日は庭の木を眺めたり剪定したり、ゆっくりとした時間を過ごしました。
それから畑に入り、今年これからのことを色々思案しました。
 この季節に咲く蝋梅はとても華やかです。花言葉は「慈愛」「思いやり」
この季節に咲く蝋梅はとても華やかです。花言葉は「慈愛」「思いやり」
先月のYOMIURI ONLINEに「ICTで農業普及目指す 県、来年度から研究へ」という記事がありました。
神奈川県が来年度から、ICT(情報通信技術)を活用して収穫量の増加や作業の省力化を図る「スマート農業」の研究に本格的に乗り出すというものです。
トマトの栽培環境をコンピューターで制御する温室を新設して、試験栽培を通して、最も育つ条件や効率的に収益を増やす方法を分析したうえで、スマート農業の普及を目指すそうです。
藤沢市にあるトマト農園の社長さんがICTを積極的に導入しており、県がこちらの農園を参考にしているとのこと。こちらの農園では、トマトを栽培している計1haの温室7棟で、気温や湿度など室内環境を全てコンピューターで制御しています。
「室内に設置されたセンサーが、気温や湿度のほか、二酸化炭素や日射の量なども計測。データに基づき、暖房機や二酸化炭素の発生器が自動的に作動し、最適な栽培環境をつくる。日照時間などに応じ、土の代わりのロックウールにも水や肥料が自動供給され、天候に左右されず、病害発生の不安も少ないトマト作りができている」(YOUMIURI ONLINE本文より)
圃場や温室でのセンシングとデータ蓄積はされますが、制御まで出来ているところはあまり多くないですよね。センシングデータを蓄積しても制御できなければ、結局人がそのデータを確認・分析して、圃場や温室に足を運ばなければいけません。だから制御はとても重要ですね。
こちらの売上額は、お父さんから経営を引き継いだ2007年の2・6倍の1億3000万円を見込むそうです。社長さん曰く「今までの農業は経験と勘に頼っていた。スマート農業の導入で、より安定した栽培、経営につながった」
そうなんです、農業って長年の経験と勘によるものが殆どでしたよね?スポーツの世界でも「盗んで覚えろ」なんてことを言われていた時代もありましたが、今やデータを蓄積して分析・解析の上で実践していくの方が効率的かつ合理的です。
農業も同じだと思います。ただ、何でもデータに頼るのもどうかと。
昨今では「平年並み」とは何なのか分からないほどの異常気象です。データ分析と経験に基づいた農業を実践していくことが大事ではないかと思っています。
 ICTと長年の経験の融合が大事 ©christopher
ICTと長年の経験の融合が大事 ©christopher
ICTとなったら何でもかんでもICTに流れていってしまうのが日本人の悪しき慣習です。これまで何十年も農業に携わってきた先人たちの経験と知恵を教科書に、ICTの技術を融合させていくことがこれからのスマート農業かな?
小春日和の正月明け、圃場に立ってそんなことを考えました。
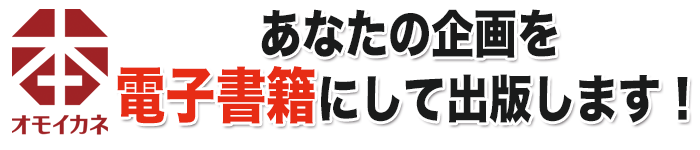
Twitterもチェック