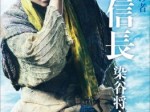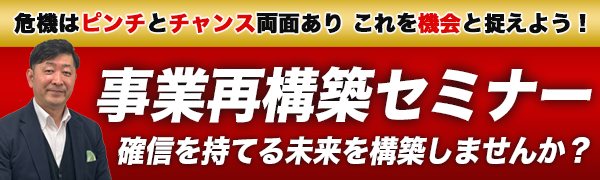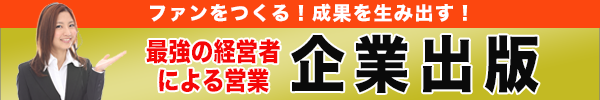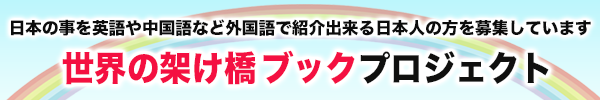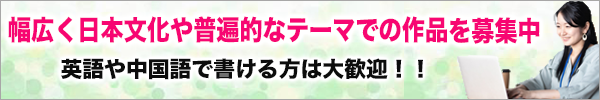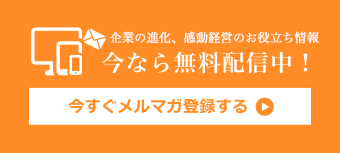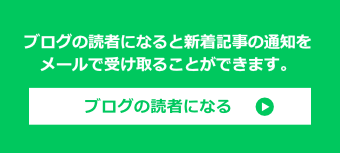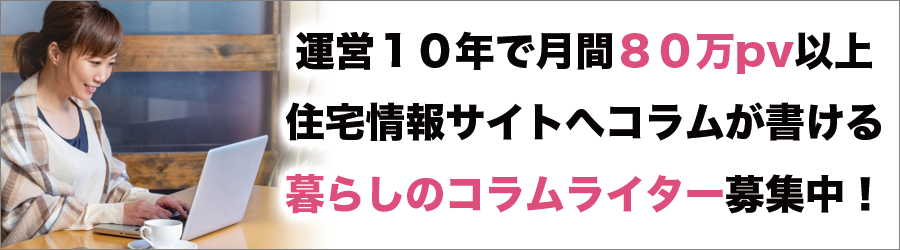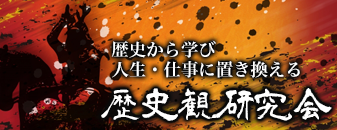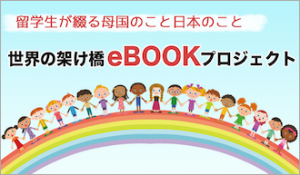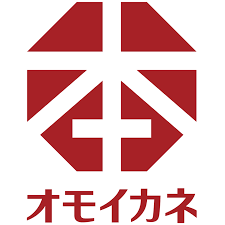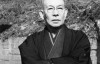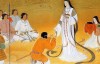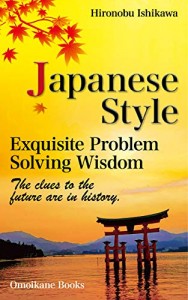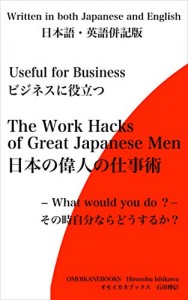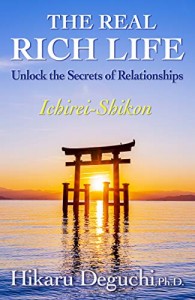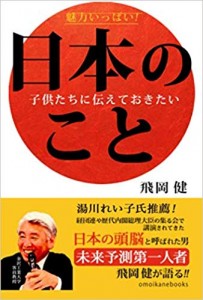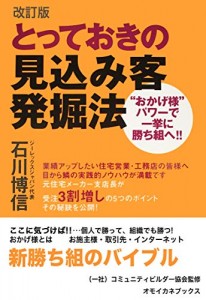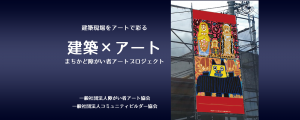日本酒の文化:お米と水が織りなす、日本の心
皆さん、こんにちは!
、私たちの国、日本が誇る素晴らしい宝物の一つ、
「日本酒」についてお話ししていきたいと思います。
「日本酒って、ちょっと敷居が高いな」
「種類がたくさんあって、どれを飲んだらいいか分からない」
思っている人もいるかもしれませんね。
でも大丈夫。日本酒は、決して難しいものではありません。
その背景にある「文化」を知ると、きっともっと好きになるはずですよ。
1. 日本酒って、どんなお酒?
まずは基本の「き」から。
日本酒は、お米と水を主原料に、
麹(こうじ)と酵母(こうぼ)を使って発酵させて造るお酒です。
ビールやワインと並ぶ、
世界でも珍しい「醸造酒(じょうぞうしゅ)」の一つなんですよ。
そして、日本の気候や風土、日本人の味覚に合わせて、
長い歴史の中で育まれてきました。
だから、日本酒はまさに「飲む日本の風土」とも言えるんです。
2. 神様へのお供えから始まった、日本酒の歴史
日本酒の歴史は、とっても古いです。
私たちが稲作を始めた弥生時代には、
すでにお米からお酒を造っていたと言われています。
その頃のお酒は、きっと今とは違って、もっと素朴なものだったでしょう。
なぜお酒を造ったかというと、
一番の理由は「神様へのお供え物」だったんです。
お米は神様からの恵みであり、
それを発酵させてできるお酒は、
神様とのつながりを深めるための、
とても大切なものだと考えられていました。
神社でお祭りがあると、今でも神前に日本酒が供えられ、
お神酒(おみき)として皆でいただくことがありますよね。
これは、まさに昔からの名残なんです。
平安時代には、貴族たちが宴会で日本酒を楽しんだり、
室町時代には、お寺でお酒造りが盛んに行われたりもしました。
そして江戸時代には、庶民の間にも日本酒が広く普及し、
各地でそれぞれの地域に合ったお酒が造られるようになりました。
まさに、日本酒は日本の歴史とともに歩んできた、
生き証人とも言える存在なんです。
3. 日本酒の味を決める、大切な要素たち
日本酒の味は、本当に多様です。
フルーティなものから、
どっしりとした味わいのものまで、
色々なタイプがあります。
この多様な味を造り出すのが、いくつかの大切な要素たちです。

- お米の種類:日本酒造りに適したお米を
- 「酒米(さかまい)」と呼びます。山田錦(やまだにしき)や雄町(おまち)、五百万石(ごひゃくまんごく)など、
- 色々な種類があり、それぞれがお酒の味や香りに個性をもたらします。
- まるで、パンを焼く小麦粉の種類が違うように、
- お米の種類によって日本酒の「骨格」が変わるイメージですね。
- お米の磨き方:お米の外側には、
- 雑味の原因となるタンパク質などがあります。
- これを削り取ることを「精米(せいまい)」と言います。
- どれくらい削り取るかで、お酒の味が大きく変わるんです。
- たくさん磨けば磨くほど、
- 雑味が少なくなり、フルーティーで華やかな香りの
- 「吟醸酒(ぎんじょうしゅ)」などが生まれます。
- 水:日本酒造りにおいて、「命」と言われるのが水です。
- 仕込みに使われる水は、
- その地域の自然によって育まれた、ミネラルバランスの良い軟水や硬水など、
- 様々です。兵庫県の灘(なだ)地方の「宮水(みやみず)」や、
- 京都の伏見(ふしみ)地方の「伏見の御香水(ごこうすい)」など、
- 名水が有名な酒どころがたくさんあります。
- まさに、水が日本酒の「透明感」や
- 「口当たり」を決めるんです。
- 麹と酵母:麹菌(こうじきん)がお米のでんぷんを糖に変え、
- 酵母がその糖をアルコールに変えます。
- 麹と酵母の種類によって、お酒の香りや
- 味が大きく左右されるんですよ。
- まるで、パンを膨らませる酵母が違うと、
- パンの風味が変わるように、
- 日本酒も麹と酵母が鍵を握っています。
- 杜氏(とうじ)と蔵人(くらびと)の技:
- そして何より大切なのが、
- お酒造りの職人さんたち、杜氏と蔵人の技です。
- 彼らは、米の状態や水の性質、気温や湿度など、
- あらゆる要素を見極めながら、
- 長年の経験と知識で最高の日本酒を造り上げます。
- まさに、経験豊富なシェフが素材の味を最大限に引き出すように、
- 杜氏の「匠の技」が日本酒の「魂」を吹き込むのです。
4. 日本酒と「季節」そして「食」の文化
日本酒は、日本の四季と深く結びついています。
- 春には、搾りたての「新酒(しんしゅ)」や、
- フレッシュな「しぼりたて」が人気。桜を見ながら飲む新酒は格別です。
- 夏には、冷やして美味しい
- 「夏酒」や「生酒(なまざけ)」が喉越し爽やか。
- 秋には、ひと夏を越して熟成された
- 「ひやおろし」や「秋あがり」が、
- 円熟した味わいを深めます。秋の味覚との相性も抜群です。
- 冬は、まさに酒造りのシーズン。
- 新米で仕込んだ新酒が誕生し、
- 温かい鍋料理とともに「熱燗(あつかん)」を楽しむのも良いですね。
このように、日本酒は季節ごとに違う表情を見せ、
旬の食材との組み合わせも無限大です。
「酒は百薬の長」という言葉があるように、
日本酒は食事とともに楽しむことで、
より一層その魅力が引き出されます。
刺身や寿司はもちろん、
煮物や焼き物、洋食にも合う日本酒が増えてきました。
5. 日本酒を楽しむための、小さな作法とマナー
日本酒を飲むときに、少しだけ知っていると、
もっと楽しくなる作法やマナーがあります。
- 器(うつわ)の楽しみ:日本酒は、お猪口(ちょこ)や
- ぐい呑み、升(ます)、ワイングラスなど、様々な器で楽しめます。
- 器によって香りや口当たりが変わるので、色々試してみるのも面白いですよ。
- 温度の楽しみ:日本酒は、冷やしても、常温でも、
- 温めても(燗酒:かんざけ)美味しく飲める、世界でも珍しいお酒です。
- 同じお酒でも、温度によって全く違う表情を見せてくれます。
- 例えば、熱燗にすることで、米の旨味が引き出され、
- 体がじんわり温まります。
- 注ぎ方・注がれ方:目上の人にお酒を注ぐときは、
- 片手でお銚子(ちょうし)を持ち、もう一方の手で軽く添えるのが
- 丁寧とされています。
- 注いでもらうときは、器を持ち上げ、
- 軽く受け取るようにしましょう。
- 無理に飲まされる文化は良くありませんが、
- 酌(くみ)を交わすことで、
- 人との絆が深まるという側面もあります。
6. 日本酒ツーリズムと、地域を巡る旅
近年、日本酒の文化は、
地域の活性化にも貢献しています。
全国各地には、たくさんの酒蔵があり、
それぞれの地域で、その土地ならではの日本酒が造られています。
- 酒蔵見学:多くの酒蔵では、見学を受け入れています。
- お酒造りの工程を見たり、試飲をしたり、
- 蔵元の方と直接お話したりすることで、日本酒への理解が深まります。
- 酒蔵ツーリズム:いくつかの酒蔵を巡りながら、
- その地域の歴史や食文化に触れる旅も人気です。
- 新潟の「越後湯沢」、京都の「伏見」、兵庫の「灘」など、
- 名だたる酒どころは、それぞれ独自の魅力を放っています。
- 地域の活性化:酒蔵が地域に根差すことで、雇用が生まれ、
- 地域の農家が酒米を生産し、観光客が訪れることで、
- 地域の経済が活性化します。日本酒は、単なる産業ではなく、
- まさに「地域の文化を守り、育む」存在でもあるのです。
事例として、新潟県の佐渡島を挙げましょう。
佐渡島は、豊かな自然と歴史に育まれた酒米の産地であり、
複数の酒蔵が存在します。近年、これらの酒蔵が連携し、
島内での酒蔵見学ツアーを企画したり、佐渡の旬の食材と
日本酒のペアリングを楽しめるイベントを開催したりしています。

さらに、若い蔵人たちが伝統を守りつつ、新しい日本酒造りに
挑戦することで、新たなファンを獲得し、
島外からの観光客誘致にも成功しています。
お米農家さんも、酒米の栽培に誇りを持って取り組み、
地域全体で日本酒文化を盛り上げているんです。
日本酒は「共感」の文化
日本酒は、一人で静かに味わうのも良いですが、
誰かと食卓を囲み、語らいながら飲むことで、
その魅力はさらに増します。
「これ、美味しいね!」
「このお酒、どんな料理に合うんだろう?」
「この酒蔵は、こんなこだわりがあるらしいよ」
そうやって、人と人との会話が生まれ、
共感が生まれる。
日本酒は、まさに「人と人、人と地域、人と自然をつなぐ文化」なんです。
皆さんも、ぜひ今日の晩酌に、
一本の日本酒を選んでみませんか?
きっと、その一杯から、日本の奥深い文化に触れることができるはずです。乾杯!