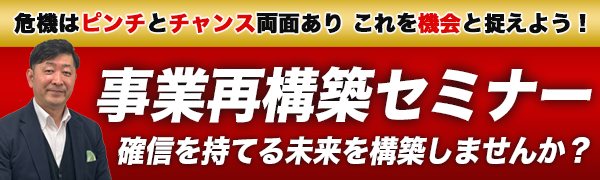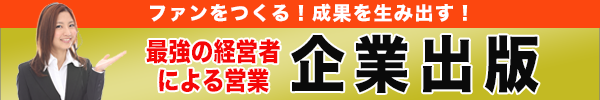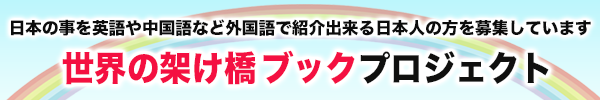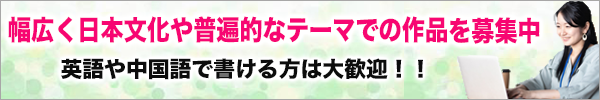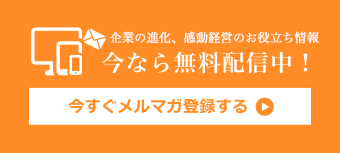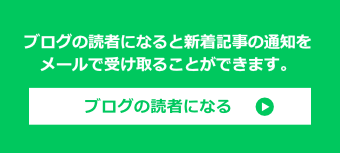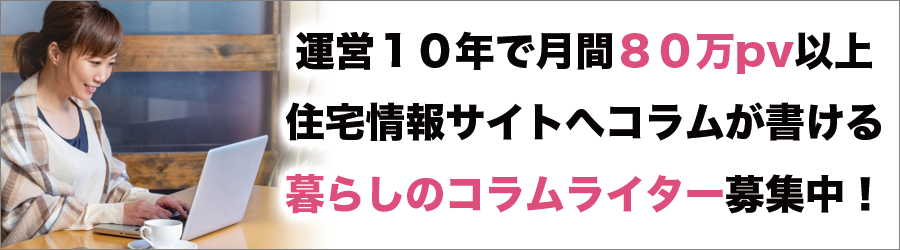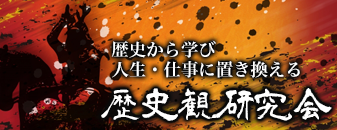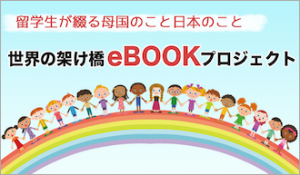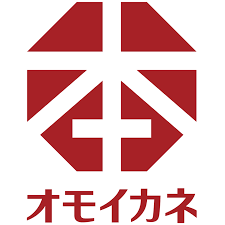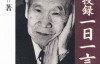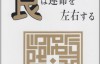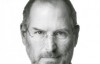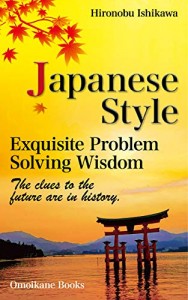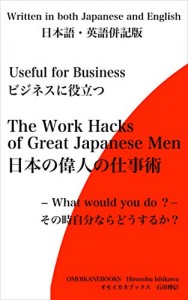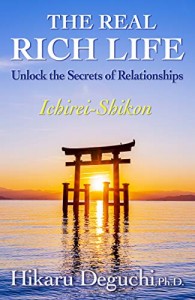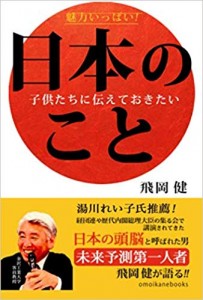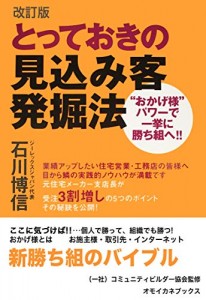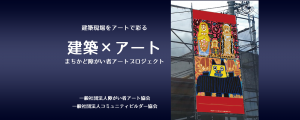醤油を海外へ キッコーマンの産業魂
公開日:
:
最終更新日:2025/09/02
未分類
今や醤油は、世界中で使われている。
しかし、キッコーマンが海外進出したときは、
知られおらず、販売には、苦労の連続であった。
なじみのない醤油を売るために、工夫もした。
焼肉にしょうゆをつけて焼いて、スーパーマーケットでデモをする。
バターに醤油を組み合わせる。
とくに、香りに惹かれる方が多く、少しずつファンを増やしていった。
この行動が、今につながてちる。
特に、アメリカではまだ反日感情があったり、
今まで食べたことない調味料に拒否反応があったり
苦労は想像に難くない。
それを乗り越えて、世界中で広がっている。
そもそも、
海外進出自体は、
やはり日本市場での限界と
海外市場での成長を見込んでの挑戦でした。
今でこそ、日本の食材は非常に評価されていますが、
それは、このような開拓者たちがいてからのこと。
もちろん、品質が良いことも前提としてある。
キッコーマンが初めて工場を建てたのは1973年。
今やしょうゆは、世界約100カ国で展開、
同社の海外売上比率は5割を超えている。
特に、2代目社長は、中興の祖といわれていますが、
苦難の連続がつづきます。
1927年の金融恐慌と、旧・野田醤油の大争議(218日)。
この二つの出来事は、「良い製品の前に、良い秩序が要る」
という当たり前を思い出させる。ボヤが起きても従業員が消火に協力しない
――そんな逸話が残るほど、当時の現場は疲弊していた。
ここで末席に座り、
しかし静かに実務を回し続けたのが、のちの二代茂木啓三郎(当時は飯田勝治)だ。
醤油は発酵の芸術であると同時に工程産業。初代啓三郎の系譜にある機械導入の前倒し
(ボイラー、圧搾機など)は、二代の時代にも一層の合理性を得る。
品質の“許容窓”(温度・圧力・時間)を決めて、ばらつきを潰す投資だ。
ここで重要なのは、投資の順番。見栄えの良い最終工程ではなく、
歩留まりに直結する“地味なボトルネック”から潰す。
結果、安定供給=ブランドの約束が守れる。
二代は商標・品質・表示を一本化し、説明責任を揃えた。
ここに初代の遺伝子――技術公開と販路協力――が効く。
秘密主義に寄らず、産業全体の底上げに寄与しながら、自社標準を“共通語”にしていくやり方だ。
これを“開放で勝つ”ブランド戦略と呼んでいる。プロダクトの話で終わらせず、
“どう使うか”まで提案して需要を作るのがポイント。
社是「産業魂」制定(国家の隆昌・国民の幸福/互助・相愛)
これは、
- 公共性の訳し方:「国家の隆昌/国民の幸福」を、意思決定の優先順位(①安全 ②品質 ③価格)に落とす。
- 互助・相愛の運用:情誼ではなく制度。標準作業・教育・表彰で“助け合い”を仕組みにする。
- 理念→KPI→手順→教育→評価:この鎖を週次で回す。理念は、回るときにだけ理念になる。
もともと家族企業だった、キッコーマンを社会性をさらに
もつ企業としていくにあたり、
- アフターレビューの1枚化:時系列/判断/影響/教訓/再発防止(誰が・いつ)を定型フォームに。
- 標準化スプリント:重要5工程を選び、チェックリスト+写真基準を2週間で試運用→翌週反省。
- ボトルネック投資:歩留まり・リードタイム・クレームの三点で“痛点マップ”を作り、先に詰める。
- ブランド整流:表示・容器・価格・販促文言を棚卸し、例外を“儀式的に”減らす(月1回の整流会)。
- 家業×企業の接続:歴史を語り継ぐ場(年1回の式)と、日常の意思決定(毎週の数値会)を分ける。
このようなことを実践していきます。
家族企業から世界企業への進化。
そこにいたるには、様々な苦労もあったでしょう。
企業の様々な課題の解決の糸口が見える気がしますね。
石川博信
最新記事 by 石川博信 (全て見る)
- 三島由紀夫1月14日生誕100年 - 2026年1月14日
- 発想の天才 信長が地元酒屋から世界的商社をつくるとしたら。 - 2026年1月11日
- 中村天風に学ぶ日々のあり方 - 2026年1月3日
セミナー・研修情報
*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。
●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから
●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます
友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
関連記事
-

-
渋沢栄一 新一万円札の顔
2020/09/26 |
渋沢栄一 新一万円札の顔 皆さんこんにちは。 今回は、明治から大正にかけ...
-

-
ビジネスの販促で本をつくってみませんか?
2016/12/10 |
出版企画創ってみませんか? ビジネスに本って役にたちます。 自費出版や商業出版と大きく分けて...
-

-
書きかけ原稿や出版企画を募集してますよ
2016/11/01 |
東京湾の海洋資源調査の写真(いや、ただの釣りともいう) 本を出したい、とりあえず書いてみた。で...
- PREV
- 岩戸開きとオモイカネの神に学ぶ「知恵」と「共創」の力
- NEXT
- 著名人、高名な方への営業アプローチ