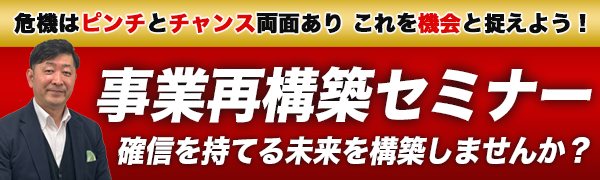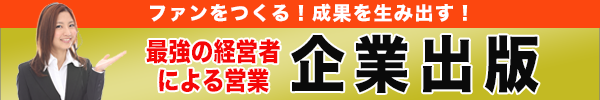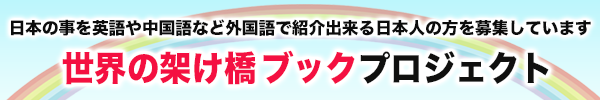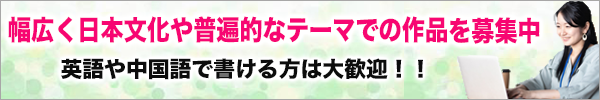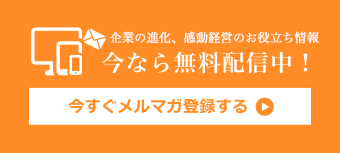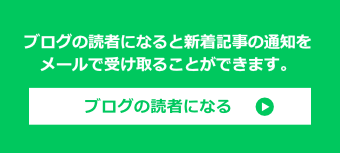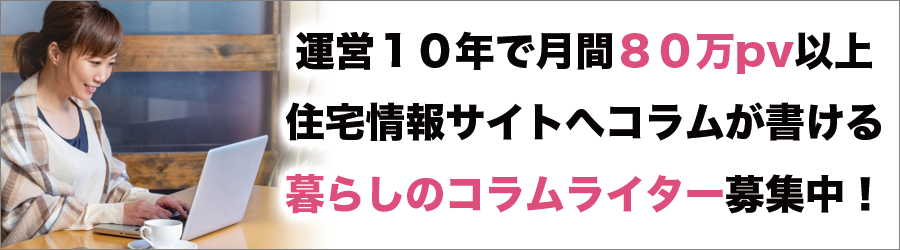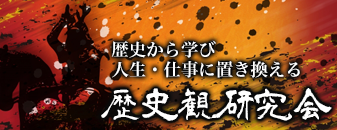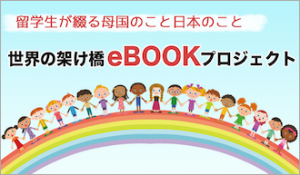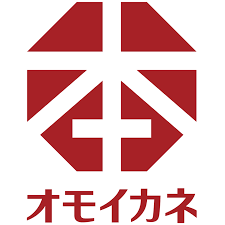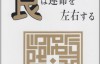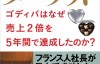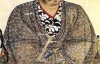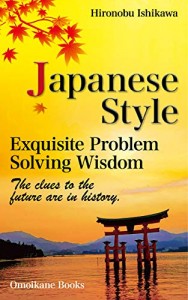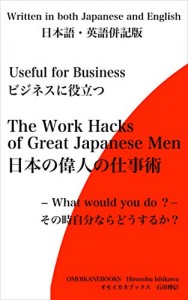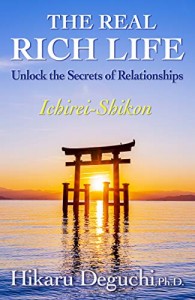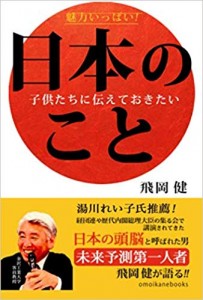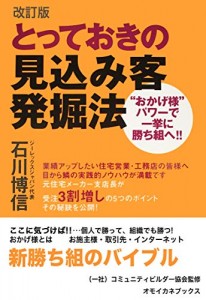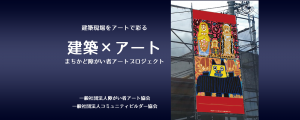古事記を読むには行間やイメージが必要かと思う
公開日:
:
最終更新日:2017/06/17
巡礼記
出雲大社の御神体を置く台座 八角形の畳です
古事記の舞台としては、高天原や出雲地方が良く出てきますね。
余談ですが、明治期まで出雲大社ではなく、杵築大社(きづきたいしゃ)と呼ばれていたそうです。
名前を変えたいきさつは分かりませんが・・。
それはさておき、古事記には様々な神々が登場しますが、その中でもやはり有名な
神様は、アマテラス、スサノオ、オオクニヌシが有名でしょうかね。
あくまで一般的な話ですが。
古事記の解釈はいくつもあるといわれているとうりで、これは
行間やイメージが出来ないと中々読んでいくことが難しいのではないかと
思います。もちろんそのままでも読めますけどね。
例えば、アマテラスの天の岩戸隠れですが、
それまでの記述どうりによめば、「お隠れになる」=亡くなったと考えられます。
しかし、古事記ではオモイカネの知恵によ岩度から再び世に出ることになります。
一般的には、スサノオの横暴に恐れをなして岩戸に隠れたということが多いでしょうが、
それ以外にも岩戸にこもられることでアマテラスは成長した。という見方や
岩戸へお隠れになった・・つまり引退、亡くなったという解釈もあります。
その前の記述を読むと、
アマテラスがイザナギから「玉」をいただいています
ここが一つポイントかなって思うんですね。
女性神といわれるアマテラスですが、イザナミの魂を引継いでいると考えられて、
さらにイザナギから「玉」をいただいたことで、男性、女性どちらの神力をいただきことになり
それがゆえに最高神と成られている。という解釈もあります。
もっとも、アマテラスが全国神社に祭られてきたのは、明治期以降の話でそれまでは
各神社ともゆかりの神様をお祭りしていました。
このあたりは政治との絡みもありそうな話なので、割愛しますが
アマテラスを最高神として現在はあること事実でしょう。
実は、この玉をもらった神様がもう一柱います。
それが出雲退大社の御祭神でもある、大国主神です。
国造りの参謀であったスクナヒコがいなくなり、海に向かって嘆いていると
光の玉があわられて、「私はあなたの奇魂、幸魂」といってオオクニヌシと一体となる。
さらに光輝く神様が来て(大物主・大神神社の御祭神)私を大和国、三輪山にまつれば
国造りはうまくいくだろう。とかたりオオクニヌシはそのようにしたという。
このあたりの解釈も色々あるところですね。
国津神の代表として、スサノオ(元々天津神だったが後に国津神へ)やオオクニヌシ、大物主、サルタヒコ
天津神として、アマテラス、ニニギなど
色々いるわけですね。
それにしても、玉を頂いている神様はアマテラス、オオクニヌシの二神ですね。
光っている、光りを放つというのは、外の神々でもあります(それでも凄いですが)が
そう考えると、大国主もほんと別格な神様ということが分かります。
僕は、大国主は日本的ヒーローの最初だと思っているので親近感はありますけど。
いづれ、古事記という書物は行間を読む、良くイメージするということを
しっかりすればホントに面白い書物で
国史なのですから、学校でも取り組んで欲しいなと感じます。
石川博信
最新記事 by 石川博信 (全て見る)
- 今を明確化にする - 2026年1月28日
- 三島由紀夫1月14日生誕100年 - 2026年1月14日
- 発想の天才 信長が地元酒屋から世界的商社をつくるとしたら。 - 2026年1月11日
セミナー・研修情報
*コロナ化の為一部個別相談としているセミナーも御座います。
●石川博信への執筆・講演・セミナーのご依頼はこちらから
●まだSNSで繋がっていない方はこちらから繋がれます
友達申請の際は一言「ブログを見ました」など頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
関連記事
-
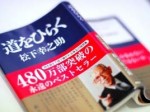
-
松下幸之助 道をひらくは永遠のベストセラー
2017/04/28 |
祈る松下幸之助 松下幸之助 道を拓く 永遠のベストセラーです。 政治家、経営者のみならず...
-

-
志事で持っておきたいもの
2017/03/13 |
きれいな朝日ですね 先月、今月と慌しい日々が続いています。 皆さんい...
-

-
中今を探る 自分は誰か
2017/04/01 |
神道の思想である「中今」 太古から受け継がれる「自分」そして未来へ向かっている自分のまさに「今...
- PREV
- 上杉謙信の言葉 手柄は足にあり
- NEXT
- 当たり前という意識は、あるという状況を創る